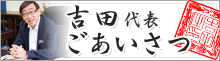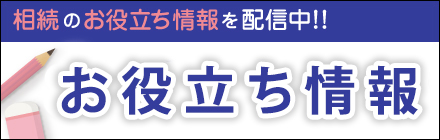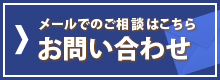相続における養子の取扱いについて 2019.11.11
相続税の計算をする際、次の4項目については、民法上の法定相続人の数を基に計算を行います。 ・遺産に係る基礎控除額 ・生命保険金の非課税限度額 ・死亡退職金の非課税限度額 ・相続税の総額 養子は民法の規定では、養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得する、とあります。 したがって、養子は養親と一親等の血族になるだけでなく、養親の実子と兄弟姉妹になるなど養親方との親族関係において二重の身分が生じます。 なお、養子の取扱いについては相続税法において一定の規制が行われています。 1つは、実子がいる場合…
住宅売却時の税金について 2019.11.5
住宅の売買には様々な税金がかかります。たとえば購入時なら登記に対する登録免許税や都道府県税である不動産取得税、消費税(土地は非課税)など。 ですが、売却時の税金に関してはあまり知ることがないのでは?と思いまとめてみました。 住宅を売却した際の利益は、所得税と住民税の対象となります。ただし給与所得などほかの収入とは分けて計算する分離課税となるため、住宅を売った翌年は確定申告が必要です。 課税の対象となる金額(譲渡所得金額)は、以下の算式によって算出。 課税譲渡所得=売却額-(購入価格+譲渡費用) …
相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産 2019.10.28
相続開始直前に被相続人が上場株式を売却していた場合、売却した上場株式は相続税の計算上どのように評価するのでしょうか。 被相続人が相続開始前に上場株式を売却していても、相続開始日までに代金決済が済んでいれば、売却代金が被相続人の財産として計上される訳ですから問題ありません。 しかし、売却をしてから相続開始の日までに代金決済がまだ終わっていない場合が稀にあります。上場株式を売却した場合、売却代金をすぐに受け取ることはできず、通常3営業日後に引渡し及び代金決済がされます。 株式を売却している訳ですから…
法人から個人へ贈与した場合にかかる税金 2019.10.23
贈与者である法人の課税関係 法人が個人にお金や物をあげた場合の取扱いについては雇用関係の有無により次のようになります。 ・贈与先が雇用関係のある従業員または役員の場合…賞与または役員賞与 ・贈与先が雇用関係のない第三者の場合…寄付金 いずれの場合も会計上の経費にはなりますが、法人税法上については従業員賞与については損金、役員賞与については原則損金不算入、寄付金についても一定額以上については損金不算入となります。 また、土地などの物をあげた場合には、その財産を時価で渡したと考えます。その為、取得価…
キャッシュレス・消費者還元事業 2019.10.15
2019年10月1日より、消費税率が8%から10%へと引き上げられることになりました。 また、同日より9ヶ月(~2020年6月)の間において、対象店舗においてキャッシュレス決済手段により商品を購入した場合、一定のポイント還元を受けられる「キャッシュレス・消費者還元事業」が行われます。 キャッシュレス・消費者還元事業は、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上・消費者の利便性向上の観点も含めたものと位置付けられています。 対象店舗は、店頭のポスターや地図アプリ(iPhohe/And…
特別寄与料の請求権の創設 2019.10.7
(1)制度概要 令和元年7月1日より「特別寄与料」を請求できる規定が施行されています。今までも相続人間の公平を図るため、寄与分として請求することは出来ましたが、相続人にのみ認められていた権利でした。 上記具体例でいうと、子Bの配偶者Eが、被相続人Aの療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、相続人でないEが寄与分を主張したり、あるいは何らかの財産の分配を請求することは出来ませんでした。感謝の気持ちで子Cや子DがEに対して何らかの経済的利益を与えた場合には、原則として贈…
土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価 2019.9.30
昨年、平成30年末に「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」という通達が新たに制定されました。 土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で一定のものとして、都道府県知事が指定するものです。 土砂災害特別警戒区域内にある宅地については、建築物の構造規制が課せられ、宅地としての通常の用途に供するとした場合に利用の制限があると認められることから、土砂災害特別警戒区域内に存しない宅地の価額に比して…
転借権、転貸借地権の相続税の評価方法 2019.9.24
人から借りたものを第三者に貸すことを転貸借といいます。 「又貸し」された人の権利を転借権といいます。 例えば、Aさんの土地をBさんが借り、BさんがAさんから借りた土地をCさんに「又貸し」したとします。 「又貸し」されたCさんの「土地を利用できる権利」は転借権となります。転借権は、借地権の上に更に借地権がある状態の事を指します。 土地を所有しているAさん、土地を借りているBさん、更にBさんから「又貸し」されたCさん、それぞれが土地に関する権利を持っていることになります。 3人それぞれが持っている権…
準確定申告とは 2019.9.18
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。故人は所得税の確定申告をすることが出来ませんので、その相続人および(*1)包括受遺者が代わって確定申告をすることになります。 申告期限は、1月1日から死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされています。 全ての人が準確定申告を行うということではなく、対象期間内の所得につき、納税額がないときは、準確定申告手続きは不要となります。 通常、次の場合には、準確定申告が必要と…
相続無料相談会を実施いたしました 2019.9.9
2019年9月1日(日)2日(月)の2日間、阪急西宮北口駅前にある「なでしこホール」で相続無料相談会を開催致しました。 当日は多くの方にご来場いただき、ありがとうございました。 「遺言書を作りたいけどどうすればいい?」「名義変更していない不動産があるけど、どうすればいい?」「生前に出来る相続対策は?」など、様々ご相談をいただきました。 また、相続が発生して具体的にどのように手続を進めていけばいいのか?というご相談もありました。 当日、ご相談に来られなかった方も随時、個別相談を受け付けています。 …
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)