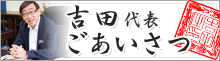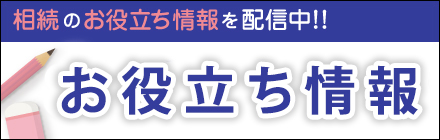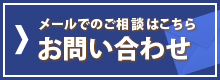相続人に行方不明者がいる場合 2018.4.25
相続人の一人のうちに疎遠になっていた親族がいますが、連絡がつかず行方不明です。 この場合、どのように相続手続きをしたらよいのでしょうか。 相続手続きに必要な「遺産分割協議」を行うには、相続人全員の参加が必要です。 まずは、専門家や行方不明者の家族に依頼し行方不明者の戸籍の附票を取得します。 現在の住所が判明したら手紙を書いたり、直接訪ねて可能な限り連絡を取ってみます。 それでも、連絡がとれない場合は、2つの方法から選択します。 その① 家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申し立て、不在者財産管…
贈与税の相続時精算課税制度 〜 第4回 2018.4.18
・2,500万円の特別控除の適用を受けるには贈与税の期限内申告が必須条件! 相続時精算課税制度を選択しようとする場合はそもそも贈与税の期限内申告が必要ですので、最初の年については忘れることはないでしょう。 一度この制度を選択すると、一生やめることはできないため、精算課税を選択した親から子に行われる贈与については極端な話、例えそれが1万円の贈与であっても、原則でいえば贈与税の申告が必要となります。 精算課税制度適用初年度に1,000万円の贈与を受けた場合、特別控除額の2,500万円以内ですので、贈…
贈与税の相続時精算課税制度 〜 第3回 2018.4.11
今回も相続時精算課税制度(以下、「精算課税」といいます。)についてのお話です。 [収益部分についても移転することができる] 例えば、駐車場として貸し付けている土地や貸し付けているアパートなどの賃貸不動産を、精算課税を使って贈与すると、不動産の所有者は不動産の贈与を受けた人になるので、そこから生まれる収益も贈与を受けた人(新たな所有者)に帰属します。 推定被相続人の財産の増加を抑えることは相続税対策という観点からも有効ですし、早期にその収益を享受できれば贈与を受ける人にとってもメリットがあります。…
贈与税の相続時精算課税制度 第2回 〜 2018.4.4
前回に続き、相続時精算課税制度(以下「精算課税」といいます。)について、ご紹介します。 ・2,500万円までの贈与については贈与税がかからない。 もしも精算課税を利用せずに親から一度に2,500万円の財産の贈与を受けたとすると、財産をもらった人(その年1月1日現在で20歳以上とします)は約810万円の贈与税を国に納めなくてはなりません。同額を暦年贈与制度で毎年こつこつ1年間の基礎控除額110万円の範囲内で贈与するとしたら、贈与税はかかりませんが20年以上の長い年月を要します。 財産を贈与する人に…
贈与税の相続時精算課税制度 第1回 〜 制度の概要 2018.3.28
今回から4回に渡って相続時精算課税制度についてご紹介していきます。 1年間に110万円の贈与であれば、財産をもらう人に贈与税はかからない、という話を聞いたことがある方も多いかと思います。これを税務上「暦年課税贈与」と呼びます。 贈与税には、「暦年課税制度」と、もう一つ平成15年に創設された「相続時精算課税制度」という制度があります。 暦年課税贈与は財産を贈与する(=あげる)人が誰かを問わず、財産をもらった人の贈与を受けた財産の価額が年間110万円を超えるか否かで贈与税の申告の要否が異なります。 …
贈与による財産の取得の時期はいつになるのか? 2018.3.22
贈与により財産を取得した場合、その贈与による財産の取得時期は、いつになるのでしょうか。 贈与税が発生する場合は、贈与により財産を取得した日の翌年に確定申告書を提出しなければなりません。 また、相続が発生した際、相続開始前3年以内にされた贈与(相続時精算課税が適用される場合を除きます)については生前贈与加算の規定により相続税の計算の対象になります。 いつ財産を取得したかというのは、税務申告をする上でとても重要です。 国税庁のホームページのタックスアンサーによると、贈与を受ける財産の取得の時期につい…
上場株式の評価 2018.3.14
今回は相続財産の中に上場株式がある場合の評価方法についてお話します。 上場株式については、今ではインターネットでその時点の価格を容易に把握することが出来ます。 相続の場合、取得した財産の価額は、原則として「その財産の取得の時における時価による」ものと相続税法第22条において規定されています。 相続の場合の取得の時は、相続開始日時点です。 では、上場株式であれば、その株式を所有していた人が亡くなった日の最終価格によるのでしょうか?その価格を把握することは比較的容易です。 相続税の財産評価においては…
弔慰金は相続税の対象!? 2018.3.8
会社勤めだったサラリーマンの方が亡くなった場合、勤めていた会社から退職手当金等(功労金等も含まれます)、や弔慰金を遺族の方が受け取る事があります。 その際に受け取った退職手当金等や弔慰金に、相続税は課税されるのでしょうか。 退職手当金等については、被相続人の死亡後3年以内に確定したものは相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。 ただし、全額が課税対象となるわけではなく、「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税になります。 例えば法定相続人が3人で、死亡退職金として2,000万円支…
広大地の評価方法の見直し 2018.3.1
続税の財産評価の中で、広大な土地を所有している場合、要件を満たすと評価減をとることができます。 これを改正前では広大地評価と呼び、三大都市圏にあるのか否か、またその地積がどれだけの規模なのかに応じて軽減額が変わります。 『広大地の評価』の適用対象の判定の為のフローチャート】→改正前 広大地評価を利用するにあたって、改正前では適用要件が曖昧で、利用したことに伴う評価減を不服とする国税局と、裁判所で争うケースも少なくありませんでした。 例えば、上記フローチャート4つ目の『その地域における標準的な宅地…
相続税の債務控除 2018.2.21
相続税の計算上、一定の要件に該当する相続人又は包括受遺者(相続人等)については、相続又は遺贈により取得する財産の価額から、被相続人(亡くなった方)が残した借入金などの債務の額のうちその相続人等が負担する債務の額を控除することが出来ます。 条文上、控除できる債務は、「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」と規定されています。例えば、ローンなどの借入金、被相続人が亡くなるまでにかかった医療費等で課税時期(相続開始日)において未払であるもの、未払の所得税・住民税・固定資産税などが該当します。 被…
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)