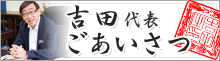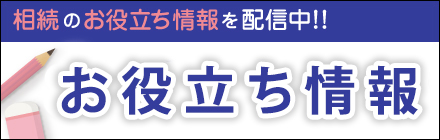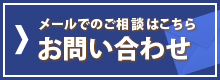ゴルフ会員権は相続財産!? 2017.12.21
相続税の計算をする上で対象となる財産は、被相続人が亡くなった日現在に所有していた財産の全てです。 案外見落としがちですが、ゴルフ会員権を所有している場合、その権利も相続財産に含まれます。 ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場を利用できる権利の事をいいます。 預託金(無利息でゴルフ場に預ける保証金のようなもの)を預けたり、株式が発行されたりするため、資産として取り扱われます。 過去には高額で取引された時代もあった為、実際にゴルフをプレーするという目的以外にも投資目的で購入されていた方もおられるでしょ…
12月度セミナー勉強会開催しました 2017.12.13
先日ハウスメーカーの社員向けのセミナー勉強会を開催致しました。こちらのハウスメーカーでは、今年は8回目のセミナー勉強会です。 今回は「不動産売買の年末契約の留意点と来年度の経済予測」というテーマでお話しました。 不動産を売ったり買ったりする場合の税務上の手続きは、契約又は引渡しを年末までにするか年を越してからするのかというのが、とても重要なポイントになります。 1日過ぎるだけで、受けようと思っていた控除がうけられなくなったり、控除できる金額が減ってしまったりという事も起こり得ますので、年末にする…
金融機関の残高証明書について 2017.12.6
相続税を計算する際に計上する預貯金の金額は、財産を持っていた人が亡くなった日現在の預入残高と、亡くなった日に解約したとした場合に受け取る事のできる利息から、利息にかかる税金を差引いた金額の合計額となります。 定期性のない預貯金については、利息の額が少額の場合、預入残高のみで評価しても差支えありません。 相続のご相談に来られる方の中には、「残高証明書は必要ですか?」と聞かれる方がいらっしゃいます。 相続税の申告が必要な方は、被相続人が金融機関に預けていた預貯金の正確な金額を調べなければなりませんの…
自分でもできる相続手続をプロに頼むワケ 2017.11.29
オアシス相続センターでは、相続に関する様々なお手伝いをしています。 ・戸籍の収集 ・銀行、証券会社の名義変更 ・相続税の申告 これらは、自分でもできる手続です。相続税の申告は難しそうですが、銀行や役所相手の手続なら頑張って自分でもできそうです。 では何故手続報酬を払ってまでプロに依頼するのでしょうか。 ご自身で手続をする場合によくありがちな失敗は、とにかく目についた手続から闇雲に手をつけてしまうことです。 必要以上に戸籍を取得して無駄になる、他で使う書類を提出してしまい取得しなおすことになる、証…
相続税の税務調査について 2017.11.23
11月に入って、国税庁から「相続税の調査の状況について」という資料が公表されました。 平成28事務年度における相続税の調査の状況について[国税庁ホームページ] これは平成28年度中に行われた相続税の実地調査について統計的にまとめられたものです。 平成26年中に発生した相続が中心ということです。 人の死亡を課税原因とする相続税という税目の性格から、税務署側も気を遣って、申告書の提出期限から1年、2年の期間を置いて調査を行うのだそうです。 相続税の申告をする際、「後から税務署の調査とかあるでしょうか…
相続税がかからなければ、相続税の申告はしなくて良い? 2017.11.13
「相続税がかからないから、相続税の申告はしなくて良いですよね?」ちょっと待った!「相続税がかからない」には様々なパターンがあります。 【課税財産の額が基礎控除額以下である場合】 亡くなった方が残した財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合には、相続税を払う必要は無く相続税の申告も必要ありません。 但し、小規模宅地等の特例などを利用して財産額を基礎控除額以下に抑えた場合で、もとの財産額が基礎控除額を上回っていたときは、相続税の申告書の提出が必要です。「この特例…
相続で沢山の戸籍を集める理由 2017.11.6
相続手続の初めの難関は、なんといっても戸籍の収集です。不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更を行う際、そして相続税の申告をする際には必ず必要な作業です。 必要書類は各機関によってそれぞれ違いますが、「被相続人の出生から現在までの全ての連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書」は遺言書が無い限り必ず全ての提出を求められます。 亡くなった方の戸籍は、生まれてから亡くなるまでのものをすべて集めなくてはなりません。年配の方であれば、戸籍法の改正ごとに戸籍が新しく…
古い申告書、棄ててもいいですか? 2017.10.30
申告が終わったら、もうほとんど見ることのない税務申告書、いつまで置いておけば良いのでしょう? 税務申告書の保存期間は、税法では7年間(法人税の赤字の申告書は9年)、会社法で税務申告書は10年とされています。ということは、税務申告書は10年保存しておけば良いということですね。では、10年を過ぎた申告書はすぐに処分してしまって良いでしょうか。 確かに、法律だけを考えると税務申告書は10年を過ぎれば棄てて良いことになります。しかし、だからといってすぐに捨ててしまうのは危険です。10年以上前の申告そのも…
時価のない財産を評価すること 2017.10.24
今回は相続税・贈与税における取引相場のない株式の評価についてのお話です。 「取引相場のない株式」とは、これは通達の言葉ですが、なんとなく字面で「非上場の株式なのかなぁ」と想像することは出来ると思います。 上場されている株式の場合は、取引時間内であればインターネットで1秒単位で時価を知ることも容易に出来ます。 しかし、「取引相場のない株式」と言っているのですから、何をよりどころに時価とすべきでしょうか?過去の取引事例も通常はないでしょう。 では、どんな人が取引相場のない株式を所有しているでしょうか…
遺留分について 2017.10.23
自分の財産を特定の人に残したい場合、遺言書にその旨を自由に記載することが出来ます。「相続人以外の人に財産を全て渡す」というような内容の遺言書も作ることが出来ます。しかしそうすると、相続人は財産を一切取得できなくなってしまいます。 基本的には、亡くなった人の遺志を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものですが、残された家族の生活を保障する為に一定の相続人には最低限相続できる財産が確保されています。これを遺留分と言います。 遺留分の計算の基礎となる金額は、基本的に被相続人が死亡時において有して…
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)