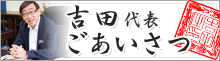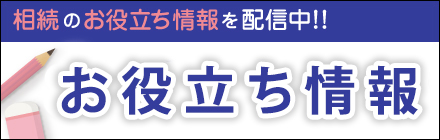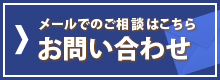遺言書が見つかった!どうすればよいのでしょう? 2020.7.20
遺言書は被相続人が自分の財産をだれに、どれだけ、どのように残すのか意思表示した文章で、遺言書がある場合、原則として相続財産は遺言通りに分割が行われます。 見つかった遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言であれば、その内容にしたがい分割をすすめますが 自筆証書遺言であればいったん家庭裁判所による検認を受けなければなりません。 遺言書の検認とは家庭裁判所がその遺言書が被相続人によるものであることを確認し、偽造などを防ぐため、遺言書の形状、訂正の状態、日付、署名などを認定をすることで内容が有効かどうか…
新型コロナ対策の給付金は課税対象? 2020.7.13
新型コロナウイルス拡大による経済対策として様々な給付金や助成金が交付されています。これらの給付金には課税対象になるものがあるということをご存じでしょうか? 今回は主な給付金の課税関係と概要を簡単にみていきたいと思います。 【非課税となるもの】 ■特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号) 国民に広く関連するのが、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人に対し、1人当たり10万円が給付される特別定額給付金です。 当初から様々な議論がありましたが、国民に確実に給付することを優先し非課…
令和2年度路線価発表の概要 2020.7.7
2020年(令和2年)の路線価が7月1日発表されました。全国平均は前年の1.6%上昇となり 、昨年に引き続き路線価は上がり、5年連続で上昇する結果となりました。 昨年2019年の路線価は全国平均で1.3%上昇。昨年より今年の方が伸び率も高くなりました。路線価が昨年から上がったのは21都道府県で、こちらも昨年の19都道府県よりも増える結果に。 特に大きく上昇したのは沖縄県で10.5%。次いで東京が5%、宮城県と福岡県が4.8%、北海道が3.7%という順で伸びました。 上昇が大きい都道府県は主に訪日…
徴収高計算書 2020.6.29
申告所得税や法人税の納付書とは異なり、源泉所得税の納付書は「徴収高計算書」と呼ばれ、源泉所得税の申告書を兼ねるものとなるため、納税額がない場合(通称「ゼロ納付」)でも、「徴収高計算書」の提出が必要となります。 電子申告及びダイレクト納付による手続きであれば特に問題はないのですが紙媒体による提出・納付を行っている場合、この「徴収高計算書」を書損・紛失等してしまうと、税務署に対し管轄署名及び整理番号を伝えた上で「徴収高計算書」を再発行してもらわなければなりません。 税務署からはごく限られた例外を除き…
新型コロナウィルスの影響により支給される兵庫県の補助金制度 2020.6.22
緊急事態宣言が解除されましたが、2020年6月時点でもまだ予断を許さない新型コロナウイルスの対策として、日本政府は2020年5月27日に第二次補正予算案を閣議決定し、6月12日に成立しました。 資金繰り対策として10兆円超を設け、事業者の事業継続の下支えのため、地代・家賃の負担を軽減する目的として「家賃給付支援金」が創設され、持続化給付金の給付対象の拡大、医療提供体制の強化など、補正予算として過去最大のものとなっています。 マスコミを通じて様々な政策をご存じかと思いますが、国以外の地方自治体も各…
遺留分侵害額の請求があった場合の相続税申告の取扱い 2020.6.15
遺留分とは、民法で定められている法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保証された最低限の相続分の事を言います。 遺言などにより、遺留分を確保出来ない法定相続人は、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来ます。 これを遺留分侵害額請求権といい、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事を知った時から1年以内であれば、本人の遺留分よりも多く財産を相続した他の相続人や受遺者に対して請求する事が出来ます。 遺留分侵害額請求により財産が減少または増加した場合の相続税…
セットバックが必要な場合の土地の評価 2020.6.8
(1)セットバックって何? 建築基準法が出来たのは1950年(昭和25年)11月23日と随分前です。 この法律では幅員4m以上のものを「道路」と規定しており、新たに家屋等を建てるには4m以上の道路に接する事が義務付けされています。 既存の家屋等が建築されている場合、即刻後退して下さいと云う訳ではなく、幅員4m未満でも家屋の建て替えをするまでは猶予するという規定があります。 そこで、その建て替え時は道路の中心線から2m後退して建築しなければならない事を通常セットバックと云います。 (2)セットバッ…
住宅取得等資金の贈与の非課税について 2020.6.1
「住宅取得等資金の贈与の非課税」は、多くの方が活用される制度だと思います。 今回は、床面積の基準についてお話します。 新築又は取得をした住宅用の家屋は日本国内にあり、登記簿上の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分があなたの居住の用に供されるものが床面積の要件になります。 (1)登記簿上表示される床面積 住宅取得等資金の贈与の特例の適用にあたっては、「登記簿上表示される床面積」で判定します。 なお、マンショ…
誰もが悩む! 居住用財産はどう相続するのが良いか? 2020.5.25
相続財産が、ほぼ自宅だけという場合 公平に分けることが難しく、遺産分割はもめがちです。 自宅の相続では、主に次の3つが考えられますがそれぞれにメリットデメリットがあります。 ①【代償分割】特定の相続人が相続する 相続する不動産に相続人の誰かが住んでいるときには効果的な方法で住んでいる相続人は住み続けることができ、他の相続人も金銭をうけとり納得できそうです。 しかし、その金銭が相続できたはずの権利に見合うものかどうかを評価するのは至難の業で、また納得できる額であった場合も、そもそもその金銭を不動産…
民法改正による配偶者居住権について 2020.5.12
40年ぶりの民法の相続法改正により、「配偶者居住権」が令和2年4月1日から施行されました。この改正は高齢化社会を背景とした配偶者の権利の拡大となっています。 配偶者居住権とは故人が所有していた居住用建物において、配偶者が終身又は一定期間、無償で居住することを認める権利です。 成立要件は以下に該当する場合です。 1、被相続人(故人)の配偶者であること 2、相続開始時に被相続人の所有していた建物に居住していること 3、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により取得したこと ≪具体例1≫ 相続人…
![神戸・芦屋・西宮でお探しなら!行政書士 オアシス相続センター[吉田博一 税理士事務所]](/wordpress/wp-content/themes/greenpoint-milanda/images/common/header/header_logo.png)